※本ページには「プロモーション」が含まれている可能性があります。
みなさま、こんにちは。
「書籍独学ブログ」の編集長「ナル」です。
今回は、世間でひんぱんに流れ始めた「リスキリング」に関わる「勉強法について」の記事です。
こんな悩みを持ったことはありませんか?
- 学生のころから、勉強はニガテ意識がある
- もともと「勉強する」という言葉自体が理解できない
- 「リスキリング」って言われても、意味がわからない
以上のことにお答えしていきます。
勉強をするというと、だれかに教わるモノだと考える人はまだいます。
しかし、社会人となってから時間を作って、学生時代と同じように勉強するのは非現実的です。
自分ひとりでも「リスキリング」が出来る方法を、向上心あるあなたにお伝えします。
今回の参考書籍↓
■なぜか「勉強」の成果が出ない社会人
学校を卒業後、多くの人たちは向上心をもって社会に出ていきます。
しかし、会社で2年も働くうちに「現状維持」に考えがシフトしてしまいます。
理由としては「このまま、現状は変わらないだろう」というあきらめです。
事実、好景気と言われるようになっても、給料が上がるかどうかは分からない。
なにより、自身に「新しい変化」が起きづらくなるのも現状です。
学生時代では1年ごとに大きな変化があります。
学校での勉強をして成績が上がらなくても、2年生、3年生へと変わります。
しかし、社会人になってからは違います。
毎日の似た業務を繰り返すのが当たり前。
1年たったからといって、昇進や業務内容の激変はありません。
だからこそ、一念発起して「資格をとって転職!」と、資格勉強を始める人もいるのは確かです。
事実、新しい資格をとると「資格取得による昇給」を認める会社は存在します。
「転職」にかぎらず、いまの本業でも役に立つのが「勉強」です。
しかし、いざ勉強を始めても「学生時代のように上手くいかない」「もともと勉強はニガテ」とする人は、途中でやめてしまいます。
なぜ、社会に出てからの勉強はうまくいかないのでしょうか?
■結局、勉強は「効率的な勉強法」を知ってるかで決まる
学生時代の勉強が出来たのは「強制力があった」から。
自分でスケジュールを決めたりせず、勉強に集中が出来ました。
当たり前です。
学校は「学びの場」。
仕事中心の場所ではなく、勉強専門の場所でした。
学校にいるだけで、勉強することが中心の生活になっています。
社会人になると、学生時代のスケジュールとはまったく違います。
仕事が中心の生活になって、仕事疲れで頭が回らないのが日常です。
それでも「勉強」は必須のこと。
なんとかしようとしても、疲れからの睡魔や明日の準備で時間がない。
少ない時間でもと勉強しても、途中で手が止まってしまいます。
学生時代とはまるで違う環境でも、勉強はしないといけません。
「資格」だろうと「転職」だろうと、勉強は必要なんです!
「だからといって、出来ない物は出来ない!」と悩むあなたへ。
次の章からは、短い勉強時間でも大丈夫な「効率重視の勉強法」をご紹介します。
■社会人でもOK!効率重視の「勉強法」5選
社会人になってからの勉強は、社会全体の課題になってきました。
「大人の学びなおし」として、政府は「リスキリング(スキル習得の再学習)の推奨」を打ち出しました。
ここからは、社会人になってから短くなった勉強時間でも
- 勉強内容が頭にのこる
- 体や精神にムリをしない
- 準備にお金や時間を必要としない
といった方法を「5選」にしてご紹介します!
勉強法1:勉強の前後に「運動」を入れる
勉強を進めていくうえでは、一番に「学習効率」を考えます。
そして「学習」において重要なのは「インプットの速さ」と「記憶に残りやすくする」のふたつです。
人体の部位でいうと「脳の情報処理能力」が重要になります。
「脳」をより効率よく性能を良くすることができると、勉強で今まで以上に結果を出せるようになるんです!
では「脳を効率良くする方法はなにか?」というと「運動」です。
それも「運動による血流の改善と向上」によって学習効率を上げることができます。
運動によって全身の血流を改善させてより流れやすくします。
一番血流が良くなる運動は「散歩」か「昇降運動」です。
どちらの運動も、足を動かしながら全身運動になっています。
しかし、どちらも屋内では満足に出来ません。
屋内でも「散歩」や「昇降運動」と同様の効果を発揮するのが「ステッパー」です。
ただの足踏みとは違い、道具を使って「ひねり」や「負担」を加えられます。
スペースも取らないので、勉強の邪魔にはなりません。
勉強法2:ポモドーロ・テクニック
次の効率的な勉強法は「ポモドーロ・テクニック」です。
「ポモドーロ・テクニック」はイタリア生まれの集中法です。
テクニックの内容は「25分の作業をして、5分間の休憩を繰り返す」というもの。
5分間の休憩中は「かるい運動」がおすすめ。
スマホや書籍など「頭を使う」のはナシ。
勉強の途中で休憩すると、学習内容が定着しやすくなります。
一番の効果は「途中のきりの悪いところで終わる」ことです。
人間の脳は「あとちょっとなのに!」と、勉強していたことに集中をはじめます。
なので、わざと途中で終わらせてしまうのも効果的。
さらには「人間の集中時間」も関係しています。
人が集中してひとつのことを続けるには、実は相当な体力が必要です。
なるべく体力を消耗しないために「わざと集中が出来ない状態」に切り替わってしまいます。
切り替わる時間が、ちょうど「約30分」!
体力切れや集中状態の切り替わりをうまくかわしつつ、集中できる!
人間が集中状態をながーく維持して勉強するのに、一番なのが「ポモドーロテクニック」です!
勉強法3:「昼寝」をスケジュールに入れる
次の勉強法は「「昼寝する」をスケジュールに入れる」です。
勉強をしていると、勉強時間を増やして「詰め込み学習」をする人がどうしてもいます。
しかし!
勉強時間をどれだけ増やしても、人間の脳のシステムに合わない方法は「非効率」です。
ねむくなってきたら寝る。
これほど単純な方法はありません。
勉強をして、集中する体力がへってきたら「昼寝」。
本当にこれだけのことで、あなたの集中するための体力は回復します。
また、人の脳は「寝ているあいだに記憶を整理する」という機能があります。
寝不足のまま勉強しても、頭には残っていません。
本当に頭のいい人は、自分の勉強がむくわれる秘訣を持っていたんです。
その秘訣こそ「昼寝をスケジュールに入れる」なのです。
ただ寝るだけではいけません。
より「効率的な昼寝の正解」をほかの記事でも紹介しています。
読んでみてください。
→「 【究極の自己投資】うまく寝るのは、一流のビジネススキルになる 」
勉強法4:高速でせまい学習範囲を復習をする
4つめの勉強法は「高速でせまい学習範囲を復習をする」です。
広い学習範囲を一度で覚えようとすると、すぐにガス欠になります。
一気に疲労を感じるので、長期的な勉強習慣も作りづらいです。
集中するにも体力は必要です。
せまい学習範囲であれば、集中の体力もそれほど使わずにすみます。
また、人の脳は「繰り返しの出来事を覚えやすい性質」があります。
勉強をするのはなんのためでしょう?
それは「結果を出すために必要なことを覚えるため」です。
であれば、勉強も「同じ範囲をなんども復習する」が正解です。
「ポモドーロテクニック」を一緒に使って「復習」を繰り返すのがベスト。
「25分でAの範囲を勉強」→「5分休憩」→「25分でAの範囲を復習」→「5分休憩」
以上の2回の復習で「1時間」。
重要なところであれば、もっと勉強する回数を増やすのもアリ。
なんどか復習が終わってから、次の範囲を勉強する。
勉強法5:1日の学習内容を「紙1枚」にまとめる
勉強法の5つめは「1日の学習内容を「紙1枚にまとめる」です。
1日の中で自分が勉強した内容を、なるべく大きな紙にまとめます。
紙にまとめるのは、またしても「復習で記憶に残す」です。
人の脳は、なんども同じことを勉強するほど「記憶に残る」ようにます。
紙1枚にまとめるのは、もうひとつの効果があります。
それは「要約する」です。
要約が出来るようになると、知識は「自分のモノ化」します。
ただ暗記しようとするよりも、自分にとって覚えやすい形にするほうが良い。
なぜなら、人には「それぞれ覚えやすい方法」が存在するからです。
よくある記憶術は「ストーリー形式」や「マインドマップ形式」。
「ストーリー形式」は、覚えたいことを語呂合わせや画像を組み合わせて「物語に仕立てる」方法。
「マインドマップ形式」は、植物の枝に似た線を書き、覚えたい知識を「数珠つなぎ」する方法。
どちらも紙に書いてまとめるのに、活躍する方法です。
紙1枚に覚えたことをまとめようとすると
- 勉強したことを思い出そうとする「セルフテスト」
- 自分なりにまとめて分かりやすくする「要約(意味:要するにこうである)」
- 手を動かして紙に書き出して、目で見て覚える「視覚記憶」
の以上3つで「効率的な勉強」が完成します。
■ナルの「編集後記」
今回、科学的な研究でわかった「効率的勉強法」をご紹介しました。
ここからは「ナルの編集後記」として
- 読んでいて気になった点
- もしかしたら、こう考えると視点が変わるのでは?
の2点についてご説明いたします。
「読んでいて気になった点」についてですが、ベストセラーになっている参考書籍は2冊とも「科学的研究が証拠にある」ということなんです。
勉強法とかを本で読むまでは「1日16時間、寝る以外は勉強をする」とか「眠い目をこすりながら、徹夜で何日も勉強する」といった「気持ちの問題」が頭にありました。
カンタンにいうと「精神論・根性論」でなんとかするというもの。
頭が良い代表の「東大受験合格者の経験」なんかでは、上記に似たような「16時間勉強」など、あきらかに生活がぶっこわれているじゃないかと疑うものがTVやネットニュースに出ていました。
ただ、勉強法そのものが科学研究されて、日本でも「勉強のやり方で苦しさは消える」というのが広まり始めた時期がありました。
受験漫画では一番有名どころの「ドラゴン桜」の人気です。
漫画がベストセラーになるのはもちろんのこと、ドラマ化して一気に日本中で大ヒット。
「ドラゴン桜」を視聴したことのある私「ナルヒサ」も「こんな勉強法ってありなの!?休憩入れながら、さらに頭に入りやすい勉強法なんてあるとは!?」と驚きました
ドラマ放映が終わった今では「「ドラゴン桜」を読んで、大学受験を合格しました!」と、満面の笑みで液晶画面に映る人がたくさんいました。
しかし、これほど「ドラゴン桜」に始まった「勉強法」が広まったのって、単純に「効率が良いよね」だけはないと考えます。
冒頭でも書いた「リスキリング」もあって、社会人の学びなおしが必要になりました。
それでも、もっと以前から「勉強法を知りたい!」と願う人は大勢いました。
ここまで「勉強法の本」が読まれているのは、読んでいるあなたも経験されたかもしれない「学生時代のトラウマ」が原因ではなかろうかと考察します。
私「ナル」も、勉強が苦手でした。
それも小学生のころからという「典型的な勉強キライ」でした。
なるべく計算問題やテストがないことを祈りつつ、学校に行っていました。
いま思えば「勉強って、なにをすれば良いのかさっぱり分からない」と、当時から悩んでいたんです。
「学生時代の勉強トラウマ」って、なにも日本国民のうち少人数ではありません。
なぜなら「勉強法を知りたい人=勉強でつまづいたことがある人」なんです。
結論、勉強法の本が増えてきた理由は「勉強をきちんとしたかった人のリベンジ」だと考えます。
これからも似たジャンルのベストセラーは、どんどん出版されるでしょう。
似た内容のものばかりかもしれません。
それでも、勉強法を知りたいと思って行動することは、何歳になっても素晴らしいことです。
※「勉強のリベンジをしたい人」には、もちろん「ナル」も入っております。
読んでくれたあなたと一緒に、行動を積み重ねていきます!
まとめ
ここまでいかがだったでしょうか?
今回は「効率的な勉強法のコツについて」を書いてきました。
科学の研究で、人間がより効率よく学習する方法はこれからたくさん出てくるでしょう!
現在、出ている方法が自分で合わないと悩んでいても、大丈夫です。
かならず、あなたに合っている勉強方法のテクニックが出てきます。
今後の出版物にも、期待がふくらみます。
待ち遠しいですね!
今回は以上で終わります。
読んでくださり、ありがとうございました。
「編集長・ナル」
〇X(元Twitter)をやっていますので、コメントがありましたらどうぞ♪
お待ちしております。
「Twitterアカウント:@naru_dokugaku」
先月(12/1~12/31)のアクセストップ6記事
第1位「【人生の先取り】「世界の名言100」を読んでみた感想を書いてみた」
第2位「【メモするだけ】1枚の紙に「考え」を書き出すと、人生は好転しはじめる」
第3位「【目的のない人生も良い】人生に目的をムリに探そうとすると損をする」
第4位「【ひろゆき氏推薦】世界で稼げる「プログラミング」の重要性と必要性」
第5位「【年末年始】大掃除で「開運する人・不運になる人」の掃除のやり方と特徴※片付けの手順も紹介」
第6位「【後悔への考え方】人生のやり直し:もし過去に戻れたら」
- タイトル:脳にまかせる勉強法
- 著者名:池田義博(いけだ・よしひろ)氏
- 出版社:ダイヤモンド社
- タイトル:絶対忘れない勉強法
- 著者名:堀田秀吾(ほった・しゅうご)氏
- 出版社:アスコム
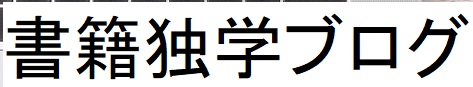
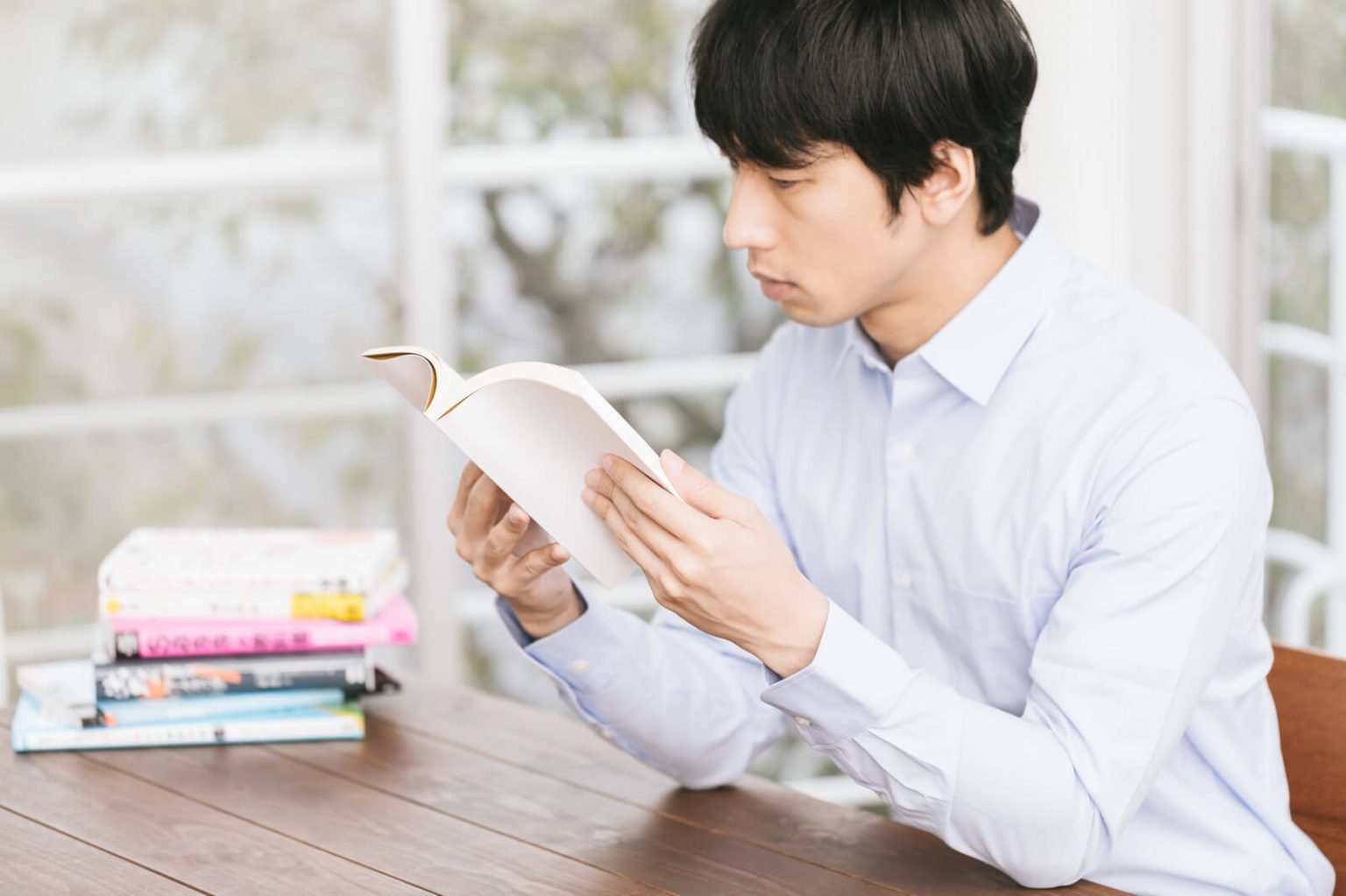


コメント