※本ページには「プロモーション」が含まれている可能性があります。
みなさま、こんにちは。
「書籍独学ブログ」の「ナル」です。
突然ですが、みなさまの家やお部屋は「片付いて」いますか?
自分の持ち物と家族の物は、しっかりと分けられてスッキリしていますか?
「散らかっているのが当たり前」になっていませんか?
上の質問に「ドキッ!」とした方にとって、今回の記事は「読む価値アリ」です!
また「片付けの基本ルール」というタイトルを見て、記事を読んでくれるあなた。
あなたは一般の人よりも「自分の生活を良くしたいと考えている人」でしょう。
とても素晴らしいことです。
今回の記事を参考に、ご自分のまわりの環境をより良いものにしていってください。
■片付けのルール”1”「しまっている物を全部出す」
片付けのルール”1”は「しまっているものを全部出す」です。
多くの「片付けられない人」の共通点は「いま、持っているものがなにかわからない」ということです。
同じものをなんども買っている人は「同じものを持っている」ということに気づいていません。
なぜなら、収納の奥のほうへとしまったは良いものの「いつのまにか忘れている」からです。
忘れてしまったため、いくつも同じものを買ってしまうんです。
片付けで最初にすべきは「全部出す」
片付けをして生活を変えるのであれば、始めにすべきことは「全部出す」です。
あなたが片付けたいと思っているところからでOK。
家中の棚をひっくり返してから、夜遅くに寝る場所がないなんてことがあってはいけませんから。
「いまは、ここだけを片付ける!」と、口に出してはじめてみましょう。
家族と住んでいる人はわかると思いますが、人の片付けほど工夫の無さか見えてしまいます。
家族と一緒に住んでいるときの片付けは、自分のところだけで良いんです。
家全体を片付けるには「片付けの経験値」が必要になります。
手に負えない事態、たとえば人の物を壊してしまったなどがあってはいけません。
一番ハードルの低い「自分の物の片付け」から始めましょう。
ひとつひとつを片付けるようにすると「片付けの経験値」は積み重なっていきます。
自分のところが片付いたのなら、次は「共有の場所」へ。
1人暮らしの人であるならば、とにかく全部出して「なにをどれだけ持っているか」を確認です。
人を呼ばないといけない事態になっても良いように、片付けましょう。
■片付けのルール”2”「「使う物・使わない物」に分ける」
「片付けのルール”2”」は「「使う物・使わない物」に分ける」」です。
片付けのルール1「全部出す」で出した物のなかから、今度は「仕分け」をしていきます。
全部出したのは「なにをどれだけ持っているか」を知るためでしたね?
出した物をよく見てみると、同じ物が複数あったり似ている機能の物がふたつみっつも。
さらに状態を確認すると「ボロボロ」だったり「シミ・カビだらけでさわれない」なんてこともあります。
あなたは「ボロボロ」だったり「大量にある同じ物」にこう思うでしょう。
「もういらない・・・」
重要ルール「使う物・使わない物」に分ける
そこで重要なルールが「「使う物・使わない物」に分ける」です。
あなたの「今の生活の理想」を思い描き、使う物だけを残していきましょう。
片付けのときは「エリア分け」をすると、作業がしやすくなります。
部屋の半分にエリアを区切り「左半分が使う物、右半分が使わない物」と決めてみましょう。
「全部出す」で出し切った物を「ひとつずつ」分けていきましょう。
いらない物、すでにゴミになった物を手放すのは、はっきりいって「快感!」です。
あなたの部屋が、捨てていくだけで理想の部屋へと変貌していきます。
どんどんゴミ袋や箱にまとめていくとき、とても興奮しているかもしれません。
興奮して楽しいでしょうが、一度たちどまってみましょう。
大切な物、思い出の物も一緒にまとめて手放してしまうと、これからの人生でおおきな後悔になります。
かならず、物を仕分けて手放していくのは「ひとつずつ」。
片付けを「楽しいイベント」として、これからもおこなっていくのに必要なことです。
「物を分ける・手放すときはひとつずつ」が、後悔しないルールといえます。
ただし「注意」もあります。
あなたが手にとった物を「前もとっておいたから」という理由で残してはいけません。
手元に残すかは、かならず「今のあなたの理想にとって「使う物」か「使わない物」か」を考えてみましょう。
■片付けのルール”3”「使う物は、すぐに使える位置に収納する」
片付けのルール”3”は「使う物は、すぐに使える位置に収納する」です。
片付けのルール”2”の「「使う物」と「使わない物」に分ける」で分け終わった「使う物」。
分け終わったあとは、再収納します。
出しっぱなしにするわけにはいけません。
生活空間であるなら、家事や移動するときに物にぶつかる可能性があります。
「お気に入りだから」「すぐに使うから」と出しっぱなしにしていると、いつか壊してしまうかもしれません。
「使う物」であっても、きちんと収納しておきましょう。
使う物は「すぐに手を伸ばせるところ」へ
実際に「使う物」を再収納するときは、かならず「すぐに手が伸ばせるところ」を選びましょう。
毎日使うとわかっているのに奥の方へと収納しては、出すだけの作業に体力が尽きてしまいます。
いつも自炊しているのに、包丁や鍋を出しづらいところに入れてはいけません。
「やる!」と決めた瞬間には目に見えるところに配置しておきます。
勉強したい人は「筆記用具・ノート・教科書や参考書」をワンセットにしておく。
読書を楽しみたい人は「背表紙が見える配置」を。
仕事をしたい人は、引き出しに「PC・メモ・ペン」だけを入れておくなど。
「使いたい物が使いたいときにすぐ出せる・思い出せる」が一番大切です。
実は、引き出しやケース、箱に「たまに使う物」を再収納したあとに問題が起きやすいんです。
それは「”どこ(これ)”になにをしまったんだっけ?問題」です。
カンタンにいえば「しまい忘れ」です。
- 使いたいものがどこにあるのか?
- しまったあと、どこに置いたのか?
- たくさんあるケースの引き出し、なにが入っていたっけ?
- おなじ箱ばかりで、物を出す気力が無くなってきた・・・
上記の悩みはすべて「なにを、どこに入れてあるのか」が明確になると解決できます。
一番いい解決方法は「ラベルを貼る」です。
市販のラベルメーカーやラベル用シールを活用するのもアリです。
しかし、片付けを続けていれば収納場所は変わっていきます。
家族構成や引っ越しで大きな生活変化があったとき、どうしても収納場所を変えないといけません。
(いちいちラベルを貼っていたら、家具も傷むしシール代もかかる)
ラベル作りがラクになる「養生テープ」
ケースや箱、引き出しに貼るラベルにおすすめな商品をご紹介。
それは「養生テープ」です。
「養生テープ」は「はがすことが前提のテープ」なので、貼り直しがカンタンに出来ます。
またガムテープのように売られているので、たくさん使っても一回の購入で済むこともあります。
よく台風前の防災として窓に「バッテン(×)」のテープが貼ってあるのを見たことありませんか?
あの「窓のバッテン(×)」こそ「養生テープ」。
カンタンにはがせるのに、粘着力はしっかりしてます。
ここでは「使う物の再収納」について書いてきました。
まとめると、
- 毎日使う予定がある物は、すぐに手が届くところにおく。
- 自分の目的にあわせて「勉強セット・仕事セット」など、物をまとめておく
- しまった場所がわかるように、ケースや引き出しに「ラベル」を貼ることをおすすめ
- 「ラベル」には「養生テープ」を使うと、家具を傷めずにすむ
の以上です。
次は「使わない物をどう仕分けるか」についてです。
■片付けのルール”4”「「使わない物」は「大切かどうか」で残す」
片付けのルール”4”は「「使わない物」は「大切かどうか」で残す」です。
- 「人からの「いただき物」だけど、もう使わないなぁ」
- 「かざるだけのインテリア、どうしよう」
- 「思い出がいっぱい詰まってるアルバム、かさばるけども」
なんて悩み、捨てる直前で考えたことありませんか?
もったいなくて使わんかった物や記念品、旅行のおみやげって「飾るだけ」だから「使わない物」ではあります。
しかし「思い出のものは捨てた戻ってこない」というのも事実です。
もうお亡くなりになった人からいただいた物は、ふたつとない大切な物です。
捨ててはいけない「大切な物」の基準
あなたが「使わない物はすべて手放すべきだ」と考えているなら、ちょっと考え直してください。
「あきらかなゴミだから使わない物」なら手放していいのです。
ただ「使わないけど、手放してしまったら・・・」とためらうものなら一度おちつきましょう。
捨てる前に「あなたにとって”大切な物”かどうか」を明確にしてみませんか?
先ほども「亡くなった方からいただいた物」とたとえに出しました。
使わないからといって、なんでも手放すべきではありません。
「そこにあるだけで心が嬉しくなる」
「持っているだけで安心する」
人それぞれに「持っているだけで良い物」があります。
インテリアグッズ一個とっても、あなたにとって「大切な物かどうか」で仕分けをしていきましょう。
片付けをする理由は「あなたの理想の生活空間」を作ることです。
自分にとって「使わないけど大切な物」は、しっかりと残してOKです。
■片付けのルール”5”「使わなくて大切でない物」は手放す
片付けのルール”5”は「「使わなくて大切でない物」は手放す」です。
ここまでの「片付けのルール」をおこなってきたあなたの手元には「使わなくて大切でない物」がのこりました。
部屋のなかはすっきりとしていて、理想とする生活にグッと近づきました。
あとは「手放す」だけです。
実は、わざと”ある単語”を使わないで記事を書いてきました。
片付けやミニマリズムをテーマにした書籍には当たりまえに書かれています。
それは「捨てる」の言葉です。
今回の記事を書くにあたって「片付ける=捨てる」にしたくないと考えています。
「なんでも捨てれば解決される」という「人を不幸にするかもしれない思考」はナシです。
自分の物だけでなく、家族や友人の物まで「良いこと」のように捨ててはいけません。
あなたに「片付け」を伝えるのに「捨てりゃいいんだ」とは優しくない。
なので「物をゴミとして捨てる」という事務的な作業ではなく「これまで感謝を物にこめた手放す=解放」という表現にしました。
いままでお世話になった物を「ゴミ」として扱うより「今までお世話になったありがたい物」と考える。
すると、罪悪感よりも感謝の気持ちで満たされます。
また「手放す」という言葉には「複数の物との別れ方」が含まれるんです。
「手放す」というのは「あなたのもとを去る」という意味なので、直接「捨てる」につながりません。
実際に「手放す」をするときの選択肢・一覧
実際に「手放す」というときの選択肢は以下のとおり。
- 売る→「ネットフリマやリサイクルショップ」
- ゆずる・あげる→「家族や友人」
- 寄付→「必要としてくれる団体・活動」
- 最後に捨てる→「人にあげられないものを処分する」
と、多岐にわたる「手放す」があります。
あなたのもとにある「使わなくて大切でない物」をどう手放すか、考えてみてはいかかでしょうか?
■まとめ
ここまで記事を読んでいただき、本当にありがとうございます。
今回のテーマは「片付けの基本ルール」でした
コロナの影響で「巣ごもり」が多くなり、家のなかに目が届きやすくなりました。
我が家でも片づけを始めてますが、これほど「片付け方のおさらい」が重要な時代になるとは。
今までは「機会があったときにだけ片付けよう」と考えていたのが「コロナ」でひっくり返りました。
外出がしづらくなった今だからこそ、家の中を「より良い生活空間」にする重要性が増しています。
今回の記事が、あなたにとって「より良い生活」のキッカケになってくれたら嬉しいです。
今回は以上で終わります。
「ナル」でした。
〇X(元Twitter)をやっていますので、コメントがありましたらどうぞ♪
お待ちしております。
「Twitterアカウント:@naru_dokugaku」
先月(12/1~12/31)のアクセストップ6記事
第1位「【人生の先取り】「世界の名言100」を読んでみた感想を書いてみた」
第2位「【メモするだけ】1枚の紙に「考え」を書き出すと、人生は好転しはじめる」
第3位「【目的のない人生も良い】人生に目的をムリに探そうとすると損をする」
第4位「【ひろゆき氏推薦】世界で稼げる「プログラミング」の重要性と必要性」
第5位「【年末年始】大掃除で「開運する人・不運になる人」の掃除のやり方と特徴※片付けの手順も紹介」
第6位「【後悔への考え方】人生のやり直し:もし過去に戻れたら」
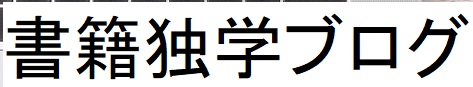



コメント